お金が貯まらない人は路上の小銭に関心が薄いようです。
一方、お金が貯まる人は小銭はもちろん、名刺1枚さえも大切に扱います。
両者の行動の違いが数十年積重なると、とんでもない格差が生まれることになります。
目次
1. タイの路上で放置されている少額コイン
私は日本が寒い時期、タイの別荘で過ごしています。
1~2月のバンコクは毎日が晴天、暑すぎないうえに、物価は日本の1/2~1/3。
とっても過ごしやすいです。
物価が安いということは、国の所得が低く貧しい人が多く存在することになります。
そんな発展途上のタイでも、別荘から最寄り駅の道中で小銭を拾う機会があります。
もちろん、拾うのは1バーツ(約4円)か5バーツ(約20円)の少額コインです。
その頻度は週1~2回。
探すために歩いているわけではなく、目的地に着くまでの数分の間に目にするのです。
タイ人の平均所得は日本の約1/3。財政的に裕福な国ではないのに、少額コインが軽視され路上に放置される傾向があるのです。
2. 小銭を軽視する困窮者、小銭を軽視しない富める者
ここ2年間で私が訪れた国は「タイ」「スリランカ」「フィリピン」「ミャンマー」です。
硬貨が流通していないミャンマーは別として、どの国でも小銭を拾う機会がありました。
特に驚いたのは、フィリピンの貧しい人が大勢集まるエリアに、まとまった小銭が砂に半分埋もれていたことです。
といっても1ペソが4枚、日本円にして約8円ですが‥‥(汗)
発展途上国、貧しい人がいるエリアでは、小さなお金が奪い合いになるイメージがありましたが、現状は見向きもされていないようでした。
その日暮らしでお金に困る生活をしている人が小銭を馬鹿にして拾わない。億万長者が、それを拾い集めて買い物の足しとして使う。結果として放置されていた小銭は貧しい人の足しになるのではなく、富む者の足しになったのです。
お金が貯まる人は、普段から名刺1枚はもちろん、クリップ1個、コピー用紙1枚、お金以外のこともシビアにとらえています。
細かい出費まで考えているからお金が残るのです。
逆に考えていない人は無駄な支出を減らすことができなため財産を築くことが難しいのです。
いたって簡単なロジックです。
3. エレベーターの中で1セントを拾ったのは世界1の投資家
ニューヨークのウォール街のビルの中に落ちていた1セントを拾い上げたのが、世界1の投資家ウォーレン・バフェットだったという逸話を聞いたことがあります。
アメリカで1セント(ペニー)は軽蔑される傾向があります。
その軽視されているものを周囲に人がいる状況で、拾い上げることができたのは、お金に対する強い執着心があるからこそです。
拾い上げたバフェットが発した言葉は「10億ドルへの第一歩さ」。
ここで言った言葉に関しては諸説ありますが、私なりの解釈をすると「拾ったのは1円、しかし、これを複利で100年回せば、バカにできない金額に膨らむんだ」。
つまり、バフェットは複利と長期運用を見据えて膨らんだ将来の資産のことを言ったのだと思います。
本当に資産を増やしたい人は、自分の財布から出ていくお金にシビアになります。
また、余剰の資金を複利でまわすことで自分が労働していない間に資産を増やすことを考えます。
本気で資産を増やしたいと思う人は1円を軽視しないのです。
そもそも、1円玉も100万枚集まれば100万円の価値になります。
4. 遺失物横領届作成に使われる税金と警察官の労力
拾ったお金を交番に届けないと「遺失物横領」という罪になります。
では、日本全国で落ちている小銭を見つけた人が、バカ正直に交番に駆け込んだら全国の警察は僅か数円の落とし物のために書類作成することになります。
1枚の書類作成に15分かかるとしても100件あれば25時間。
1年で9000時間以上使うことになります。
警察官の時給が2000円だと仮定すると小銭の遺失物届処理に年間1800万円の税金が使われることになります。
警察官に9000時間書類を作成してもらうくらいなら、捜査や道案内に使ってもらった方が国としても助かるはずです。
話のスケールが小さすぎて、この辺りに関して、発言する人を見かける機会がありませんが、改善するか、意識の共有をした方がいいと考えます。
まとめ
お金持ちは、小銭を軽視することなくお金として扱います。
軽視していないからこそ路上で見向きもされない小銭を拾い上げて、経済活動の中に戻すことをしているのです。
軽視している人、軽視しない人。両者に違いが出るのは当然の結果なのです。
※落とし主が解る可能性があるモノは良心に従って交番に届けてください


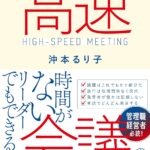





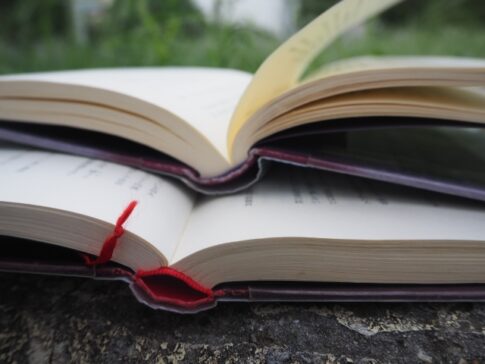






コメントを残す