オイルショックや流行り病、社会の不安が高まるとき、マスクやトイレットペーパーが店頭から消ます。
品薄になっていることがテレビ等で放送されると、商品を求める人が押し寄せて、商品の入手をさらに難しくします。
つまり、騒動中は、混雑する店頭に出向いて入手するか、安くない小売品をコンビニ等で購入することになります。
「余分な支出をしない」、「不要な混乱に巻き込まれない」、「自分の身を危険にさらさない」ためには普段から非常事態に備えておくことが大切なのです。
目次
1. 忘れ物が許されない南極行動で学んだ準備の大切さ
私が自衛隊のミッションで南極に行ったとき、半年分の日常生活品を準備しました。
生活の基本となるのは南極観測船「しらせ」。
食事の提供、寝床、お風呂、トレーニング施設等は完備されていますが、衣服やシャンプー、石鹸、歯ブラシ、洗剤、お菓子や清涼飲料水は個人で準備します。
日本を出国したあとに忘れ物に気付いた場合は、2週間後に寄港するオーストラリアで購入。
それ以降は、モノを補充できないため忘れ物は絶対許されません。
「忘れ物ができないのであれば、何でも多めに持って行けばいい!」という発想になりますが、個人に与えられているスペースはロッカー1個に共同で使える倉庫スペースだけです。
出国前まで、個人が持っていく荷物の取捨選択を重ねて半年の航海に臨むのです。
2. 備蓄量が1年を切ったら2年分を補充
半年間の南極行動を経験したことで、身の回り品を備蓄する考え方が変わっていました。
a. 物はいつでも購入できるとは限らない
b. 消費期限のない日用品は1年以上の備蓄する
c. 大量のストックを収納するためにデッドスペースを活用
我が家では、トイレットペーパー、石鹸、歯ブラシ、下着、カセットガスなどの日用品を1~3年分ストックしています。
在庫数が1年を下回ると、商品を安く買える場所を検索して、楽天かドンキホーテで2年分まとめ買いしています。
オンラインショッピングで注文する場合も、まとまった量の商品を購入して、無料で配送してもらうようにしています。
3. 備蓄品を無駄にしないローリングストック
乾パンなどの備蓄品を準備しても、結局、使わないまま消費期限が過ぎて捨てた。
不適切な保存で、使おうとしたときに役に立たなかった。なんてこともあります。
備蓄品は格納したままにするのではなく、古い物を使いながら在庫を消費する「ローリングストック」がとっても有効です。
「購入した新しい商品を既存の備蓄品と入れ替えるのが面倒くさい」と思われる方もいると思いますが、入れ替えが大変なのは、カセットガスくらいで、他の物は重くないので苦になりません。
また、非常事態時、ティッシュペーパーやキッチンペーパーはトイレットペーパーで代用。
リンスやトリートメントは使わない、シャンプーやボディーソープは石鹸で済ませる。
洗濯洗剤は、マグネシウムの力で汚れを落とし、すすぎ不要な「洗濯マグちゃん」を使うなど、備蓄品の種類を増やさないことが大切です。

4. 非常事態が発令された直後に入手するのは生鮮食品
非常事態が発令されてから、日用品をそろえているようでは、あなたも、あなたの家族も大変に困ることになります。
誰しもが物不足に陥ることを防ぐため、売り場はごった返しになるはずです。
そもそも、オンラインストアが開いていても買った商品が届けられるのかも疑問です。
近所のスーパーに向かったとしても道路寸断されている?
買い物できる商品数が制限されている?
クレジットカードで支払うことができるのか?
1万円札で支払ったらお釣りがある?
大量に買っても持ち運べない?
など、普段では起こりえない問題が発生している可能性があります。
日用品備蓄が済んでいる家庭は、肉や野菜、果物を入手することに集中する。
余裕があればガソリンを満タンにして、あとは、家で籠城するだけです。
平時から備蓄品を整備しておく、少額紙幣、小銭を準備しておく、非常時にとる行動を想定しておくことが大切です。
まとめ
国が非常事態宣言を出したあとは、ATMの現金は直ぐになくなり、店の商品が売り切れる、ガソリンスタンドは長蛇の列ができまるうえに、治安が悪化すること予想できます。
不測の状況下で苦労しないためには、平時に非常事態に対する準備をしておくことです。
まずは、混乱する店内で日用品を買わなくても済むように備蓄しておくことが大切です。
備蓄ができている家庭が増えれば、店頭での混雑、商品の奪い合いも減ることになります。
「備えがあれば憂いなし」、心に余裕があれば非常事態を乗り切ることができるはずです。
※大量のストックを収納するためのデッドスペース活用術については次回リリースの予定

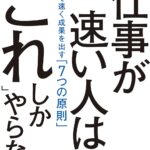



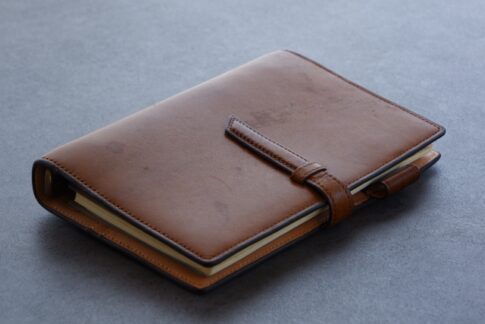
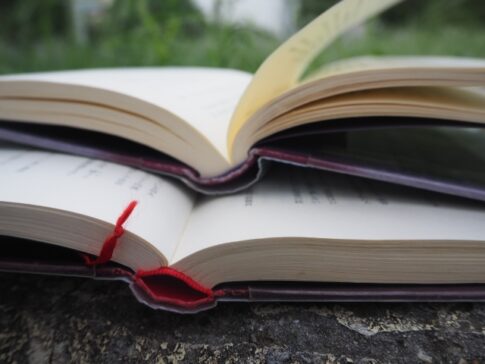







コメントを残す