流行り病等による外出制限が発表されると食料品や日用品の棚は空になります。
また、大規模災害に見舞われたあとは、店頭から商品が消える他に水道やガスなどの生活インフラが止まり、日常生活に大きな支障が出ます。
発生時期や場所を予想することはできませんが、起きたあとに備蓄品がある家とそうでない家庭では、被災後の生存率が大きく変わります。
今回は、「確保しておきたい食料品の量」と「保管場所として活用したいデッドスペース」についてお伝えします。
1. 農水省が推奨する備蓄の量は3日+α
「農水省が推奨する各家庭の備蓄量は3日」「できることなら1週間が望ましい」と発表されています。
災害などの大惨事が起きると食料生産が止まります。
生産が再開されても、物流が止まる確率が高いため、必要なモノが店頭に並ぶまで時間がかかりモノ不足に陥る可能性は高い。
そのため、日頃から備蓄しておくことが大切です。
では、農水省がアナウンスするとおり「3日あれば足りるのか?」
もちろん、災害や非常事態の規模により異なりますが、十分とは言い難いです。
東日本大震災のとき被災地に救援物資が届き始めたのは発生8日後。
発生後7日間は、捜索救難中心に活動するので仕方ありません。
つまり、確率は低いですが、被災した場合1週間程度の食料が必要となるのです。
2. 大人1人が1週間生きるのに必要な食料は4㎏
食料供給がストップした場合、大人1人に必要な食糧は週4㎏です。
水道、ガスが使えて、家に引き込もった状態でカロリー消費を抑えられる場合の試算です。
大人1人、1日米2合を食べると7日間で14合。
1合の重さが約150g=1週間に2.1㎏必要です。
副食に缶詰1個90g。1日3缶270g。7日間で2㎏近くの重さになります。
もちろん、大人2人なら米4キロ、缶詰4キロ。
家族が増えれば増えるほど必要な食料が増えることになります。
米と缶詰で算出しましたが、実際は飽きるので、米の代わりにスパゲティーやアルファ米。
副食にカレーやお惣菜のレトルトを食べることを考えると、多品種の食材を用意することになるため必要な備蓄の量は増えることになります。
※今回は、水道、ガスが使える想定で算出しましたが、使えなければガス缶や水の備蓄が別途必要になります。
3. 備蓄に必要な収納スペース
平時の食料品は高いモノではありません。
2万円も出せば4人家族が1週間必要な食材を備蓄できます。
厄介なのは保管するスペースの方です。
自宅が戸建ての方は、庭に小屋や物置を設置して収納スペースにする。
マンションにお住まいの方はベランダに、小型の物置を置くことも可能です。
難しいのは狭いアパート、社宅で生活される方です。
賃貸物件に暮らす方に、取入れて欲しいのがデッドスペースに棚を設置することです。
といっても、キッチリ、キレイに仕上げるモノではありません。
モノを立体的に置くのに必要最低限の強度を持つ簡易的なモノです。
私は、本棚を作成したときに余った木材の切れ端で、シンク下に細長い棚を設置しました。
ペットボトルが出し入れできる高さの横板を設けて棚の上に缶詰や調味料、コーヒーを置くことで収納力を増やしながら使い勝手をよくしました。
4. 空間を使い切る収納術と工夫
お米は2ℓのペットボトルにつめ替えて収納します。
ペットボトルに移し替える手間は必要ですが、劣化や虫の侵入を防ぐことができます。
四角いペットボトルを使うことで空間を無駄にすることなく縦に収納できます。
塩はフライパンで炒ってサラサラの状態で500mlのペットボトルにつめます。
水分を飛ばすことで、固まらなくなるほか、ペットボトルの注ぎ口からふりかけるので、指で摘まむ必要がなくなり、毎回、指を洗う手間がなくなります。
海自艦艇で勤務していたとき、与えられた狭い空間をどのように使えば快適になるのか?
常に考えていたので、このようなデッドスペースの有効利用ができるようになりました。

まとめ
非常事態に備え、備蓄品を準備するにはスペースが必要です。
デッドスペースに棚を設置するだけで、収納量と使い勝手を高めることができます。
始めの1個を作るのがとっても面倒に感じますが、1個作成すると使い勝手の良さに驚いて次を作りたくなるものです。
是非、1個だけでも作成してみてください。


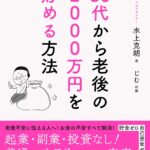





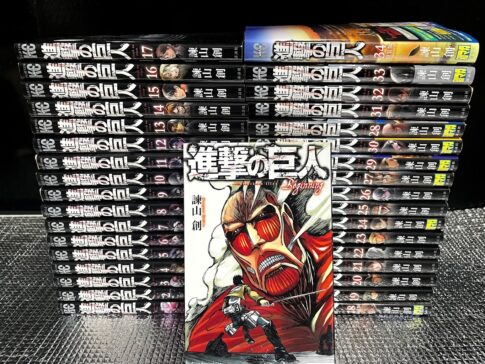
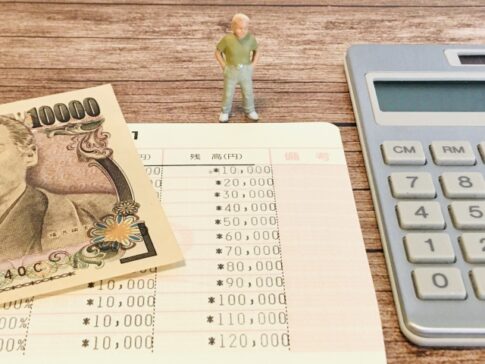






コメントを残す