日本人の家計金融資産のうち現金預金の占める割合は52.4%。
アメリカ13%、スウェーデン13%、カナダ21%と比べると高いことが解ります。
一見すると「いいこと」のようにも見えますが、そのように解釈した人は、残念ながら資産を目減りさせることになります。
1. 貯金は国を発展させるための国策
日本人は子供の頃から「銀行にお金を預けることがよい」そんなイメージをもっています。
金融資産において貯金が占める割合が他国に比べ高いのは、国が戦争資金を集めるのに必要だった国策だったといわれています。
日中戦争が始まった翌年の昭和13年、国民貯蓄奨励局が設立され国民に預金することが推奨されたのが始まりです。
発展途上国が、列強に飲み込まれないために、使えるリソースをかき集め国難を乗り越えるための苦肉の策だったのでしょう。
また、太平洋戦争敗戦後も国を復興させるのに、家庭のタンスに眠っているお金を銀行や郵便局に預けてもらい、資産を活用したことが国の再建の助けになったようです。
つまり、日本人の持つ「貯金=いいこと」の背景はこのような歴史があるのです。
2. 値上がりする物価と銀行金利の差が目減りする資産額
バブル経済崩壊後の1990年代初頭から2010年代初頭までの経済低迷期間を「失われた20年」と呼びます。
物価上昇が低調となり、モノの値段が横ばいとなった時期です。
IMF(国際通貨基金)の公表しているデータを見ると、日本のインフレ率は94年から1%を割り1997年2014年以外はマイナスか横ばいを続けています。
しかし、いくら横ばいが続いているといえど、毎年平均0.5%程度は物価が上昇しているのですから、10年で数%は物が高くなったことになります。
そもそも、2012年に安部総理が掲げたインフレターゲットは年2%。
国が2%のインフレに向けて異次元緩和をしているのですから、物価が上昇するのが自然の流れです。

なぜ、私が、物価指数を気にしているのかというと、現在の普通預金の金利が0.001%だからです。
もし、物価上昇が年0%で、銀行金利が1%であれば資産は1%増えますが、物価上昇が0.5%で銀行金利が0.1%であれば、差額0.4%、資産が目減りするからです。
つまり、利子を生まないタンス預金はもちろん、上がった物価より低い金利に預けた預金は資産が減ることになるのです。
3. 目減りする資産を補う、プラスの投資
フランスの経済学者ピケティが世界20か国200年分のデータを分析して書いた著書『21世紀の資本』によると、投資により増えるお金は年4%。
労働者収入で増えるお金は年1~2%と言っています。
つまり、労働者が額に汗して働いて得るお金よりも、投資により増えるお金の方が1年に2~3%大きい計算になります。
上記のことを踏まえると、今すぐ投資を始める必要があるとは言いませんが、物価上昇に対抗できるようにポートフォリオの中に投資を入れることが望ましいことが分かります。
上昇する物価よりも高い銀行金利をもらわない限り資産は減り続けるのが世の中の常だからです。
まとめ
投資をしないと資産は目減りする。
しかし、世の中には金融商品を使った詐欺がたくさんあり、それにより資産を失う人も大勢います。
人生は何があっても自己責任、犯人が逮捕されても取り返せる原資がなければ、返金されません。
お金に関する知識を持つことが、大切であることを知ってください。





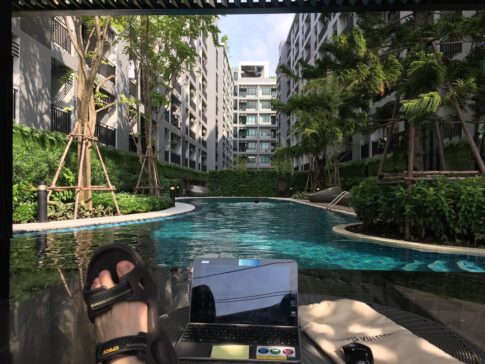








コメントを残す